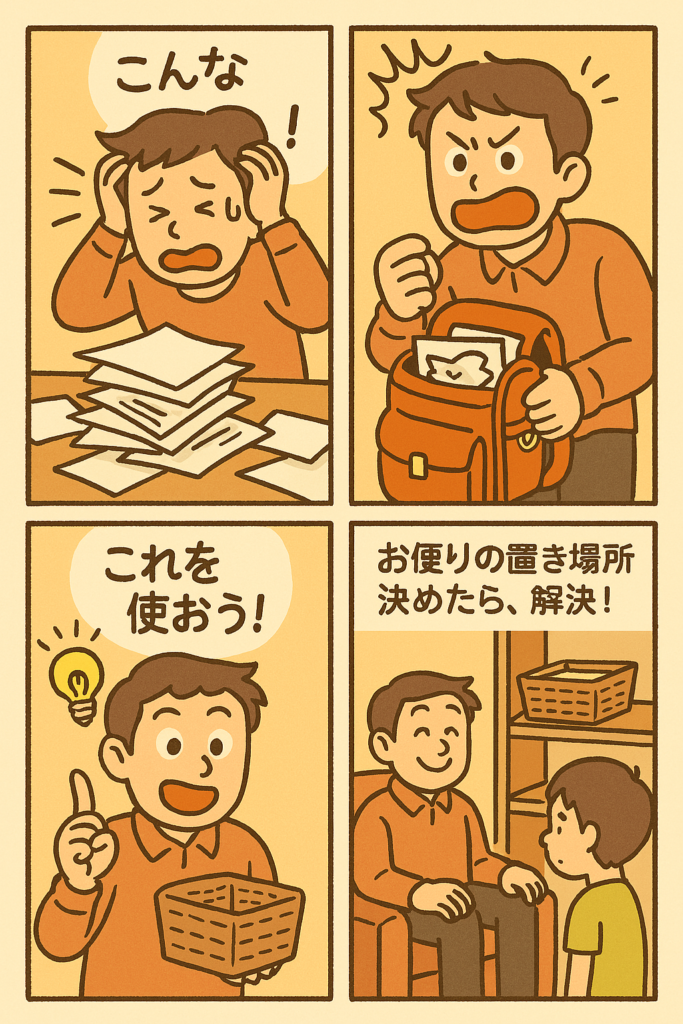
こんにちは、まっさんです!
4月、気がつけばテーブルの上にプリントの山…。
「あれ?教材の申し込みいつまでだっけ?」「これ出したっけ?」そんな“おたより迷子”に毎年悩まされていませんか?
特に共働き家庭では、夕方から寝るまでが戦場。
「とりあえずプリントだけ出して!」の声にも応えず、ランドセルの底にくしゃっとなったおたよりを見つけると、もうため息しか出ませんよね…。
でも、いくつか小さな工夫をしただけで、わが家のおたより迷子はかなり減りました。
今回は、忙しい家庭でも取り入れやすい「紙管理のちょっとした工夫」をご紹介します!
【1】“見るだけボックス”をつくる
まずは、子どもがプリントを出しやすい場所に「おたよりボックス」を用意しました。
・クリアファイルでも
・100均の書類ケースでも
・小さなカゴでもOK
ポイントは、“読んだ後で戻さない場所”と割り切ること!
つまり、「ここに入ってる=まだ読んでないもの」として、親が見る用のボックスにします。
子どもには「ここに入れてくれたらOK!」と伝えるだけ。
最初は忘れることもあるけれど、定位置があるとだんだん習慣になります。
【2】提出期限はスマホでリマインド
おたよりを読んだら、提出期限・持ち物・イベント日などは、即スマホにメモ!
おすすめは
・Googleカレンダーに登録
・リマインダー機能で前日に通知
・色分けして「学校」カテゴリを作る
「今メモしないと絶対忘れる」という前提で動くことで、〆切当日の朝に焦ることが減りました。
【3】“保存したいプリント”は1冊にまとめる
献立表、年間行事予定、学級通信など、保管しておきたい紙って意外とありますよね。
これも迷子にならないように、1冊のA4クリアファイルにまとめて「保存版プリントブック」を作っています。
インデックスをつけると見やすくて、夫婦間でも共有しやすいですよ。
【4】見せてくれない子には“親からランドセルチェック”もOK
高学年になってくると、逆にプリントを全然出してこない子もいます。
うちもそうだったので、今では「週末だけは親がランドセルチェック」と決めました。
金曜の夜や土曜の朝に、プリントや提出物を一緒に確認。
「あ、これ出してないじゃん〜」と笑いながらできると、怒るよりずっとスムーズです。
【5】「出すこと」より「出しやすくすること」を意識する
「ちゃんと出して!」と繰り返すより、出す仕組みをつくることの方が、実は効果的でした。
・ボックスを定位置に
・出したらOKルール
・親が早めに確認できる時間帯の把握
子どもに任せすぎず、かといって全部親が背負わないためにも、“ゆるく整える”のが続けるコツかもしれません。
【まとめ】
プリント管理って、ほんの少し仕組みをつくるだけで、ぐっとラクになります。
完璧じゃなくてもいい。「あれ?あの紙どこ行った?」が減るだけで、気持ちにも時間にも余裕が生まれます。
新学期の今こそ、紙まわりの小さな見直し、してみませんか?